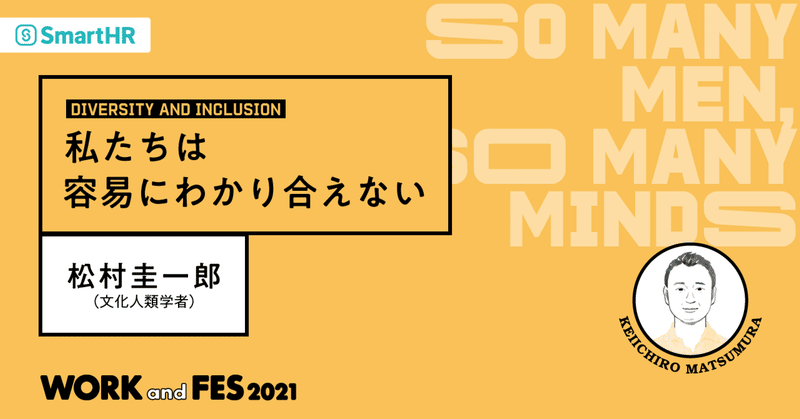
「私たちは容易にわかり合えない」松村圭一郎インタビュー#WORKandFES2021
マジョリティとマイノリティ、健常者と障害者、男と女―コインの裏表のような二元論で語られることが目立つ多様性の問題。しかし実は、それぞれの事柄の間には無数のグラデーションがあり、その一つひとつに思考を巡らせることが必要になります。それをなおざりにして形だけの多様性を実現したとしても、単なるパフォーマンスにしかならず、真の意味で創造性に満ちた組織をつくり出すことはできないでしょう。そして、コインの裏表はちょっとしたきっかけで裏返ることも知っておかなければいけません。自身のマイノリティ性に気づいたら、不慮の事故に遭遇したら、性的自認が変化したら。いつ訪れるかもわからない不確実性と向き合うための知恵を身につけるために「D&I(ダイバーシティ&インクルージョン)」について考えます。
※このインタビュー記事は、2021年12月11日に開催されたオンラインイベントWORK and FES 2021のノベルティ「WORK and FES 2021副読本」に掲載しているものです。そのほかにも、多彩な面々のインタビュー記事が掲載された副読本のプレゼントキャンペーンを3/4(金)〜3/31(木)まで実施しています。ご希望の方はこちらのフォームよりご応募ください。
私たちは容易にわかり合えない
D&Iをテーマにすると、自分とまったく異なる人々をどのように受容していくのかといった話になりがちですが、実はものすごく身近なところに考えるヒントがあります。そのことを教えてくれたのが、文化人類学者の松村圭一郎さんです。すでに引かれている境界線に疑いの目を向けて、別の線を引いてみる。それによって見えてくる関係性について考えます。

松村圭一郎(まつむら・けいいちろう)
文化人類学者。岡山大学文学部准教授。所有と分配、海外出稼ぎ、市場と国家の関係などについて研究。著書に『うしろめたさの人類学』(ミシマ社)、『はみだしの人類学』(NHK出版)、『これからの大学』(春秋社)、『くらしのアナキズム』(ミシマ社)など。共編著に『文化人類学の思考法』(世界思想社)、『働くことの人類学』(黒鳥社)がある
──松村先生は異文化と関わる機会が多いと思うのですが、どのようなアプローチからはじめることが多いのでしょうか。
そもそもの「異文化を知ろう」という態度について疑うことでしょうか。
たとえば「外国人のことを理解する」という言葉の裏には「日本人のことは理解できる」という前提がありますが、はたしてそれは本当なのか。ちょうど今、大学で卒業論文や修士論文の指導をしているのですが、なかには留学生もいて日本語を直さないといけない場面があります。では、日本人の学生はどうかというと、こちらもまったく書けていない。なんなら、留学生のほうが上手に書けていることすらあります。
私たちは無意識のうちに「日本人なら日本語ができる」「外国人は日本語ができない」と考えてしまうのですが、実はそうとはかぎらないんですね。同じ言葉を話し、同じ文化のもとで生きているはずの「日本人」であっても、均質ではなく、すごく多様性がある。それは「外国人」とされる人も同じです。ただ、社会的には、「日本人」と「外国人」のように制度などによって半ば強制的に線が引かれてしまう。
たとえば、私たちは「健常者」だと思って生きているわけですが、本当に「健常」なのかはグレーな部分が多い。「階段が上れない」という状態をひとつ取ってみても、もともと足が悪い人は「障害者」の枠に括られてしまいますが、足腰の悪くなったお年寄りや、怪我をして松葉杖をついている若者だって容易には上れませんよね。逆に目の不自由な方が、目の見える人よりも周囲の環境の変化を敏感に感じとれることすらあります。
人は変化しうる存在だし、「健常」や「障害」といったカテゴリーのなかに固定されて生きているわけではないんですね。
物事の線引き基準は容易に変化してしまう
──松村先生の話を聞いているうちに多様性という概念が揺らいできました。
世の中はわかり合えなさで満ちています。それは男女の違いとか、人種の違いとか、国籍の違いとか、世代の違いだけにかぎる話ではなく、同性や同世代のような同じカテゴリーに括られる場合でもそうで。生活をともにしている家族や仲のいい友人でも理解できないことが往々にしてあると思います。D&Iは「私たちは容易にわかり合えない」ということに向き合うとてもハードルの高い行為なんです。だから、制度だけ整えて表面的なダイバーシティを実現したとしても、何も起こらないのではないでしょうか。
──とはいえ、企業がD&Iに取り組む場合、どうしても制度的なものの整備からはじまることが多いですよね。
そこに難しさがあります。先ほど話したとおり、私たちの社会は制度的な線引きによって物事が決められることが多いのですが、生身の人間はそう簡単に線引きできるものではありません。会社が大きくなればなるほどいろんな価値観を持った人が入社してくるし、もともと価値観が近しかった人でも時間が経つことで変わっていくこともあります。そうして次々に生まれてくる差異をどうポジティブなものに変えていけるか。たとえば、会議で自分と違う意見が出たときにそれを可能性と捉えるか、ハードルと捉えるかで組織の在り方が決まっていくでしょうね。
「同じ意見です」は変化を生まない
──価値観が似ている者同士だと意見が合致して盛り上がってしまうことがありますが、そうすると違う意見を言い出すのが難しくなり、盲点に気づけなくなってしまうことがありそうです。
ノリが合うことがある種の抑圧装置になってしまう危険性はあります。会議の場は微妙な差異があふれていて当然なのに、同質であることを求めてしまう。でも、そんな組織でクリエイティブな仕事ができるかというと疑わしいですよね。
私のゼミでも同じようなことが起こるので、「同じ意見です」は禁止にしていて。それぞれ違う環境で育ってきたわけだから、まったく同じということはないはずなんです。だから、1ミリでも違うことを言う。それが素朴で素直な意見であればあるほど、みんなが気づかなかった盲点を突くことがあります。その積み重ねによって、その場がポジティブに変化していくと私は思っています。
──そこで難しいと感じるのは、組織の場合は評価という軸があることだと思います。ノリが合わない人は評価されにくい、軽んじられるといったことがあるかもしれません。
一定の基準で人間が人間を評価することは、まさに制度的な線引きのひとつですが、それがいい芽を摘んでしまうことがあるんですよね。
画家で装丁家の矢萩多聞さんという方がいます。とてもすばらしい絵を描くのですが、小学校・中学校の美術の成績は5段階評価でほとんど1だったそうです。なぜかというと、締切までに作品を提出できなかったから。ただ、小学5年生から6年生にかけて担任を受け持った石井先生のときだけは、提出期限を区切らずにいてくれたので楽しく絵を描けたそうです。
このエピソードも多様性みたいなものとつながりますよね。一定の基準で評価できないものは評価しないという態度が、可能性を潰しているかもしれない。逆をいえば、多様性を認めるということは一定の基準で評価できないものをどう見守るのかということでもあります。
仕事は決められたタスクをどれだけ正確で効率的に進められるかによって評価が分かれますが、あらゆるものに点数をつけて勝ち組と負け組に分けていくと、コミュニティの分断を生んで長期的にはパフォーマンスが下がっていくような気がします。
──数字で評価できない領域があることを評価する側が理解する必要がありそうです。
評価軸から外れた人は落ちこぼれなのかということですよね。先ほどの矢萩さんの例と同じように。もちろん、数字で評価することが求められる場面もあると思いますが、それと同じくらい数字で評価できないことに励んでいる人についても理解する必要があると思います。
一定の基準で評価できないものをどう見守るのか
──組織のジレンマを感じました。評価の話もそうですが、こうしてD&Iの重要性が世界的に説かれている一方で、アメリカではワクチン未摂取の従業員を解雇するような動きがありますよね。組織は最大多数の幸福を叶えるためにある種の排除の要素を持ち合わせているんじゃないかなと感じます。
気が合わない人は排除すればいいと考える人もいるでしょうが、組織においては同質性が高まれば高まるほど異質性が目立つようになるので、排除を続けた結果として組織から誰もいなくなってしまう。
これはよく出す事例ですが、日本には普通学校と特別支援学校というものがあって、健常者と障害者に振り分けられてしまうわけです。そして、普通学校に通う子供たちは障害者と接することがほとんどないまま大人になるわけですが、もしかしたら多様性について学ぶ機会を奪っているのかもしれないですよね。
イタリアでは、精神病院が精神病患者を生み出しているという考えのもと、1980年代には精神病院が廃止されたんですね。障害者のようなラベルをできるだけ付けないようにした。すると、子どもの頃からいろんな人に囲まれて過ごすことになるので、みんなで楽しく遊ぶ方法について知恵を身につけていくわけです。
たとえば、これは私自身も経験がありますが、野球をして遊ぶときも年齢が下の子や腕力がない子は通常より前でボールを投げていいとかルールを改変してバランスを調整しますよね。そうしないと楽しく遊べない。つまり固定的なルールを一律に適用するのではなく、複雑で多様な現実に合わせてルールを変えたり、柔軟に運用したりする。組織についても同じことがいえるかもしれません。
ひとつの評価軸だけだとできる人とできない人に分かれてしまうけど、複数の評価軸を設けたら個人ごとに能力が活きる仕事と活きない仕事に分けることができて、ある分野でビリだった人が別の分野でトップになるかもしれない。新たな可能性が拓けてくるわけです。もちろん、今話したことは理想論なので、現実にはうまくいかないこともたくさんあると思いますが。
複数の評価軸を設けたら、ある分野でビリだった人が別の分野でトップになるかもしれない
──仕事には評価しやすいものと評価しにくいものがありますよね。たとえば、誰かが落としてしまったボールを拾うような仕事は数字で評価するのが難しい。でも、そういう仕事こそきちんと評価されたほうがいい気がします。
すごくいい視点だと思います。自分たちが仕事と呼んでいるものは、はたして本当に仕事なのかという問いにつながりますよね。
ここ数年で話題を集めた人類学者デヴィッド・グレーバーの著書『ブルシット・ジョブ』には、「仕事の本質はケアである」と書かれていて、その一例として2014年にロンドンで起きた地下鉄のストライキの話があります。ロンドン市長が地下鉄にある切符売り場100カ所を閉鎖すると宣言したんですね。手作業で行っていた仕事を機械化しようというわけです。しかし、彼らが実際にやっていたことの大半が道案内であったり、落とし物の管理だったりと乗客をケアする仕事で、それは機械によって単純に代替できないものだったのです。こういう話はいろんなところにあると思います。効率化を求めすぎるあまりボールを拾う人を排除したらその組織はどうなってしまうのか。よく考えないといけないですよね。
大切なのは、自分の実感を伴った言葉で考えること
──先ほどの精神病院の話もそうですが、「よかれと思って」という行為が裏目に出ることもありますよね。
よきことだと思っている人がいちばん暴力的になるんですよ。「よいことをしている」という態度がもっとも危ない。SDGsをはじめ今の社会でよきことのように語られるものに欠けているのは、「自分たちがこの状況をつくり出した張本人」という意識だと思うんです。貧困は、先進国が生み出した不均衡が問題の根幹にありますよね。だから、本来であれば申し訳ないと思うところからはじめないといけない。それなのに「SDGsに取り組んでます!」なんて高らかに宣言してしまうのは、恥ずかしくて仕方ないわけですよ。
それはダイバーシティも同じで。マジョリティが生み出した「普通」という概念がマイノリティを苦しめている。そういった認識を持っておかないと、D&Iだと高らかに言っていてもいい結果にはならないのではないかと危惧します。
──松村先生と話しているなかで、もし気が合わない人と働くことになったらどうすればいいんだろうとか、そもそもそうやって考えること自体が悪いんじゃないかとか、いろんなことを考えました。
そうやって具体的に考えていくと本当に難しいんですよ。うちの大学のなかにも僕とは気が合わないけど、学生からの信頼が厚い先生がいます。つまり、一面で考えないことが大切。自分が見ている面とは違う方向から相手を見ると気づけることもあるわけです。
そして大切なのは、自分の実感を伴った言葉で考えること。「D&I」や「ウェルビーイング」といった横文字を使ってもよくわからないですよね。自分たちが抱える問題について、それぞれの現場の状況に即して個別具体的に考えて、柔軟に行動する。そこからはじまることもあるのではないでしょうか。
文:村上広大 イラスト:星野ちいこ
本記事が掲載されている「WORK and FES 2021 副読本」のプレゼントキャンペーンを3/4(金)〜3/31(木)まで実施しています。ご希望の方はこちらのフォームよりご応募ください。
■働くの実験室(仮) 公式サイト
WORK and FES 2021を主催する働くの実験室(仮)の最新情報や裏話、実験の種が届くニュースレター登録は下記ウェブサイトから 👶
■公式Twitter
随時、情報発信中です!
